TRPGサーバー 「Sandbox」 Advent Calendar 2019 の寄稿記事です。
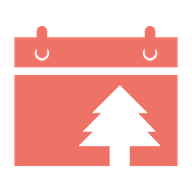
マジック:ザ・ギャザリング。世界初のカードゲームとして知られるそのゲームは、今なお多くの人々に親しまれている。最近ではMTGアリーナの登場により参入の難易度が大きく下がり、より活発化することが期待される。
そんなマジック:ザ・ギャザリングだが、コラムが連載されていることはご存じだろうか。世界設定について知ることが出来るストーリー記事。現在の環境の解説や対策が紹介される戦略記事、1枚のカードに焦点を当て、その歴史を語る今日の一枚……そのような、マジック:ザ・ギャザリングを取り巻く環境を様々な角度から切り取ったコラムが連載されている。
そのような中で、マジックに特に興味がないという卓プレイヤーの方であっても是非見てもらいたい記事が存在する。
それこそが、マジック開発秘話。マジック:ザ・ギャザリングというゲームシステムに対する試行錯誤やこだわり、テクニックなどが語られる記事群である。先述の通り、マジックは世界初のカードゲームでありそれだけノウハウを積み重ねてきている。そして、その中にはTRPGのシナリオ構築に活用できるテクニックも存在するのだ。
そこで今回、マジック開発秘話より、TRPGのシナリオに活かせそうな考え方が記載されている記事を幾つか取り上げ、紹介をさせてもらいたいと考える。
そういった試みであるので、別にマジックに興味が無かったり、トラウマがあったりする方でも安心して記事を読み進めて欲しい。
名前の通り、マジックのデザインに関する記事であり、今回の主題に非常に合っている記事。
2019年のマジックは、”ラヴニカ”と呼ばれる世界が主な舞台となっていた。このラヴニカという世界はプレイヤーからの人気が高く、都度3回、物語の舞台となっている。(1回目は2005~2006年、2回目は2012年~2013年)
そのため、ある程度決まった設定が存在し、求められているものが何か分かっている。故に作るのは簡単――とは言えない。人気の理由を維持しつつ、マンネリを避けなければいけないからだ。
この記事は、そんな難しい条件を満たす為、どのような手段を用いて、どのような結果が得られたのかが書かれている。
特に、ページ中ほどの灯争大戦は物語のクライマックスとも言える箇所の話であり、シナリオとシステムの兼ね合いについて記載されており、是非読んでもらいたい。
パーティ開催のコツとマジック:ザ・ギャザリングのデザインを関連させたコラム。
話の軸がパーティであるため、マジックをしていなくても全文読むことが出来るだろう。パーティをしたことが無い? 私もない。けれどTRPGは一種のパーティみたいなものと考えれば……これを読んでいる人であれば、全く無いということも無いだろう。
とにかく。パーティとマジックの関連性なんてものは、マジックとシナリオの関連性よりもよっぽど関連が無いように思える。しかし多くの物には共通点というものが存在し、その共通点を重ねることで、見えてくるものがある。
ここでは、テーマ(モチーフ)について話が行われているが、何がどう関係し、そしてそれがどう受け取られるのかは読んで確かめて欲しい。
プレイヤーが何を求めているのか。プレイヤーに何を与えればいいのか。
先ほどとは打って変わって、タイトルからして役に立ちそうに感じると思われる。実際その通りであり、文中の節タイトルをいくつか取り上げると、『誰もがそのゲームを好きでも、誰も愛してくれなければ失敗する』『プレイヤーがゲームで魅了されるところは細部である』『プレイヤーに挑むことよりもプレイヤーを飽きさせることを恐れよ』など、興味の惹かれるタイトルが並んでいる。
非常に面白い記事だろう。
先述のコラム(ゲームデザインでダイバーシティが必要な理由)の中にも記載があるこの記事、この記事こそ是非読んで欲しい。
この記事は2016年に書かれた記事であるが――マジックが続いてきた20年を振り返り、そこで得た教訓が書かれている。各教訓はカードデザインの話から始まっているが、カードを知らなくてもそれに付随する教訓を読むだけでも十分な糧になると思われる。
一つ難点があるとすれば、記事が非常に長い、ということだろうか。
今までとは少し異なり、マジックを形成する5つの色を擬人化させ、プレイヤーからの質問に回答するという形のコラム。
知らない人の為に少し話すと、マジックには5つの色が存在し、それぞれ得手不得手が存在している。破壊が得意な色、回復が得意な色、ドローが得意な色といった基準が存在しており――それに牽引されるように色の考え方(性格)の違いというのが設定されている。これによってカードデザインがスムーズに設定されるようになるというわけだ。
この記事は、その色に対して質問をしてみよう、という試みであり――今までとは趣が異なるものの、単純に読んでいて面白い記事だと言えるだろう。
ちなみに、この色の違いの理解度を試すことのできる記事なども存在する。
マジックを知っていれば面白い記事であるので、もし良ければ挑戦してみてほしい。
あまり多く紹介しすぎても、読む気が無くなるだろうから紹介はこの辺りにしておこう。
本当は私が好きな、ストーム値やラバイア値の話もしたいところだが、これは流石にマジックを知らないと意味が分からないため、興味のある人が調べてくれることを期待しよう。
著者:背景/背景局卓上支部
最近の禁止状況を見ると開発こそこれを読むべきだと思う。

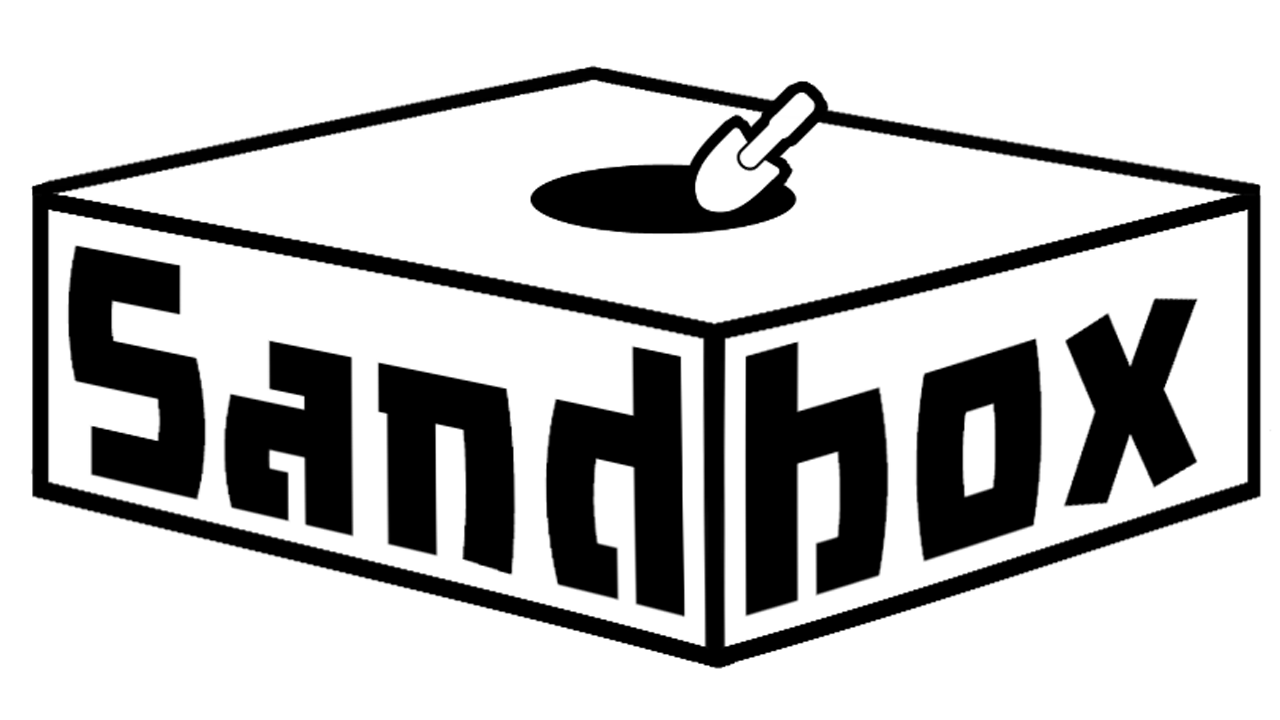

コメント