TRPGサーバー 「Sandbox」 Advent Calendar 2019 の寄稿記事です。 https://adventar.org/calendars/3873
「ロールプレイは、好きですか?」
もしあなたが好きだと言うなら、是非とも話を聞いてほしい、
もし苦手だとしたのならば、少しだけ時間を割いてほしい。
アドベントカレンダー、10日目の話は、私が好きな、とあるシステムのお話。
『平安幻想夜話 鵺鏡』はインコグ・ラボ様によるTRPGシステムであり、そのタイトルの通り、平安の都を舞台としたシステムだ。もちろんただの平和な都ではなく、空には暗雲が立ち込め、通りには妖が闊歩し、力なき人々は明日は我が身と隠れて生きる……どこか暗い雰囲気が漂う、そんな世界が舞台となる。
それを象徴するように、プレイヤーは何かを”喪って”いる。ある者は家族を奪われ、またある者は名誉を汚され……未来に希望は無く、愛はどこかに置き忘れている。あなたたちは、物語を通じてそれを取り戻していく。
それ故に、プレイヤーは対立する。そう、例えば『名誉を取り戻すために妖怪を退治する人間』と『居場所を守るため人間に立ち向かう妖怪』が同じ物語に登場したのであれば。そも目的を完遂するのはどちらか1人となるだろう。
基本ルールブックに記載されているシナリオからして『迷惑な女に惚れられている者』『その女に惚れている者』『その女に復讐を企てている者』……それぞれが別の、そして共存し兼ねる目的を持っている。
故に、決着をつけねばならない……のだが、そう。本システムには『決着をつけるシステムなんてものは搭載されていない』。
本システムは大量のD20を使用するのだが、その目的は『得点を稼いで、目標値に届かせること』。そう聞くと、「その得点で優劣を決めればいいのでは?」と思う人もいるだろう。(実際、そういったギミックを仕込んだシナリオも存在する。私も作ったことがある)
だが、本システムはプレイヤーの合計点のみを参照する。そのため、シナリオ上では対立しているプレイヤーが判定の面では協力する、なんてことも十分に、いや頻繁に起こりうる。それは、本システムが『キャラクター同士での判定ダイスの交換が可能である』ためである。
例えば、能力値10のPC1と能力値12のPC2がいるとして、PC1の出目が12、PC2の出目が10だった状況を考えるすると分かり易いだろう。そのままではPC2だけが成功となり、合計点数は1点となる。しかしPC1とPC2の出目を交換すれば、お互いに判定に成功する結果となり、合計点数が2点に上昇する。実際のシステムでは、低い出目が出ればより多くの得点が得られたり、特定の条件下で得点を増やす行動が行えたり出来る為、この交換は非常に重要な協力要素となる。
このような、シナリオとシステムの乖離こそ鵺鏡の醍醐味の一つであるが、それをより面白いものに昇華させているギミックが存在する。それこそ、プレイヤーが持っている特殊能力、”業”だ。
プレイヤーは判定の際に能力を宣言することで、判定を有利に(つまり、プレイヤー全体に有利に)進めることが出来る。もちろん、無条件に発動することは出来ない。他のシステムでもマジックポイントやパワーポイントといったものを消費しなければならないのと同様、リソースの消費を求められる。
この鵺鏡におけるリソース、それこそが……そう、そしてここで漸く、最初の話に戻ってくる。
「ロールプレイは、好きですか?」
鵺鏡の能力発動に必要な能力、それは、“ロールプレイ”である。
それぞれの能力に必要なロールプレイが設定されており、それをしない限り能力を発動することが出来ない。そのロールプレイも様々であり、”対象に切りかかる” “高笑いをする”といった基本的なものから”未来を予言する” “神を降ろす”のようなアイディアが求められる動き、”周囲に呪いを振りまく” “辺りを火の海に変える”といったシナリオを大きく動かす行動まで多岐に渡る。
そうすると、ロールプレイが苦手な方は「自分向きではない」と考えてしまうかもしれない。しかし、私としてはそれはむしろ勿体ないと考える。
このシステムは『その場に応じたロールプレイによって能力を使用する』のではなく、『使いたい能力に合わせてロールプレイを行う』ものである。つまり、判定の結果に応じて自動的に自分のロールプレイ方法が決まっていくシステムである、と言い換えることが出来る。
「何をしていいか分からないから苦手」というのであれば、能力のコストが行動の方針になってくれる。「上手くロールプレイが出来ない」のだとしても様々な能力=ロールプレイのリストから自分が出来そうなロールプレイを事前に選ぶことが出来る。
ロールプレイが出来ないから合わない、のではなくむしろロールプレイが苦手でもロールプレイが出来るシステム、と考えていいのではないだろうか。
一方、ロールプレイが好きな人にとっても悪いシステムではない。能力の発動にロールプレイが求められるということは、つまり判定を行うたびにロールプレイの機会が必ず発生するということである。もちろん、能力の発動によってロールプレイを強いられることはあるだろうが……ロールプレイが好きな方であれば、上手くそれを活用出来るだろう。
協力して得点を稼ぐため、ロールプレイを駆使して物語を進めていく……それがシステムの根幹にあるとなれば、先ほどの 『決着をつけるシステムなんてものは搭載されていない』 の意味も理解できるのではないだろうか。
物語がプレイヤーのロールプレイによって進むのならば、当然その結末もロールプレイによって決まる。そう、シナリオを通してプレイヤー間で決着を決めなければならないのだ。
対立しているキャラクターをどう動かし、どのような展開にしていくか。誰かが望みを叶えるルートを選択するのも良いだろうし、誰も目的を果たせなかったエンディングというのもまた一つの物語だと言えよう。
プレイヤーの意志と閃きに、ダイスロールの悪戯と能力の要求が複雑に絡み合って、意図しない展開を作り上げ、一つのストーリーとして組みあがる。これこそが、私が鵺鏡を人に薦める理由である。そう、おそらく、おそらくではあるが、『同じプレイヤーが同じキャラクターで同じシナリオをプレイする』としても同じ展開を迎えることは出来ないだろう。一期一会を体現した、プレイヤー達だけのシナリオがそこにはあるのだ。
そして、そんな物語を盛り上げるNPCも鵺鏡の魅力の一つだろう。
最強の陰陽師”安倍晴明”、学問と災厄の雷神”菅原道真”、六歌仙に名高い”在原業平” “小野小町”。九ツの尾を持つ大妖狐”玉藻前”、大江山の鬼”茨木童子”、タイトルにも冠された”鵺”等々……誰もがよく知る人や妖が、時に味方として、時に障害としてプレイヤーの前に現れることになる。
彼らとどう接するか、彼らがどう反応するのか……もちろん、それもプレイヤーの行動次第である。
ところで、この鵺鏡。システマチックに進めると判定の度にロールプレイが途切れることがある。これは、判定の処理の中に”能力発動ロールプレイ”のタイミングがあること、つまり”能力発動ロールプレイ”と”通常ロールプレイ”の間に断絶が出来てしまうことが原因である。
そこで、それを緩和する一つのテクニックを紹介して、本記事の締めとしたい。
とはいえ、そこまで複雑なことではなく、ただ単純に『判定の計算タイミングを変更する』ということである。ルールブックに記載されている方法では、”能力発動ロールプレイ”は判定処理中に行うものであり、”通常ロールプレイ”とは別に行うものとなっている。しかし、これをそのまま適用すると、ロールプレイの最中に判定処理が行われることとなり、現実に引き戻されてしまう。そうでなくとも、1回の判定に対して2回の中断(判定直前と能力発動後)を行うというのはGMの負担が非常に大きい。
そこで、判定の計算タイミングを『次の判定直前に行う』という手段を使うのはどうだろうか、というのが私の提案である。つまり、能力発動ロールプレイから続けて通常ロールプレイを実施、ひと段落ついたところで判定の計算と次の判定を同時に行ってしまおう、というものである。そうすると、一区切りつくまでロールプレイを続けるということが可能となり、円滑なシナリオ運びが出来る(そして、GMが無理やりロールプレイが出来るような展開を生み出す必要が軽減される)と考える。少なくとも、私はこのやり方の方がやりやすいと感じている。
とはいえ、ルールブックから少々逸脱した方法ではあるので、言わずもがな、使う時はプレイヤーの同意を取った上で使用してほしい。
そんな所だろうか。
もし、本文を読んで、一人でも鵺鏡をする人が増えるのならば、これほどうれしいことは無い。
私もPLしたいし。
著者:背景/背景局卓上支部
好きな客分は茨木童子。

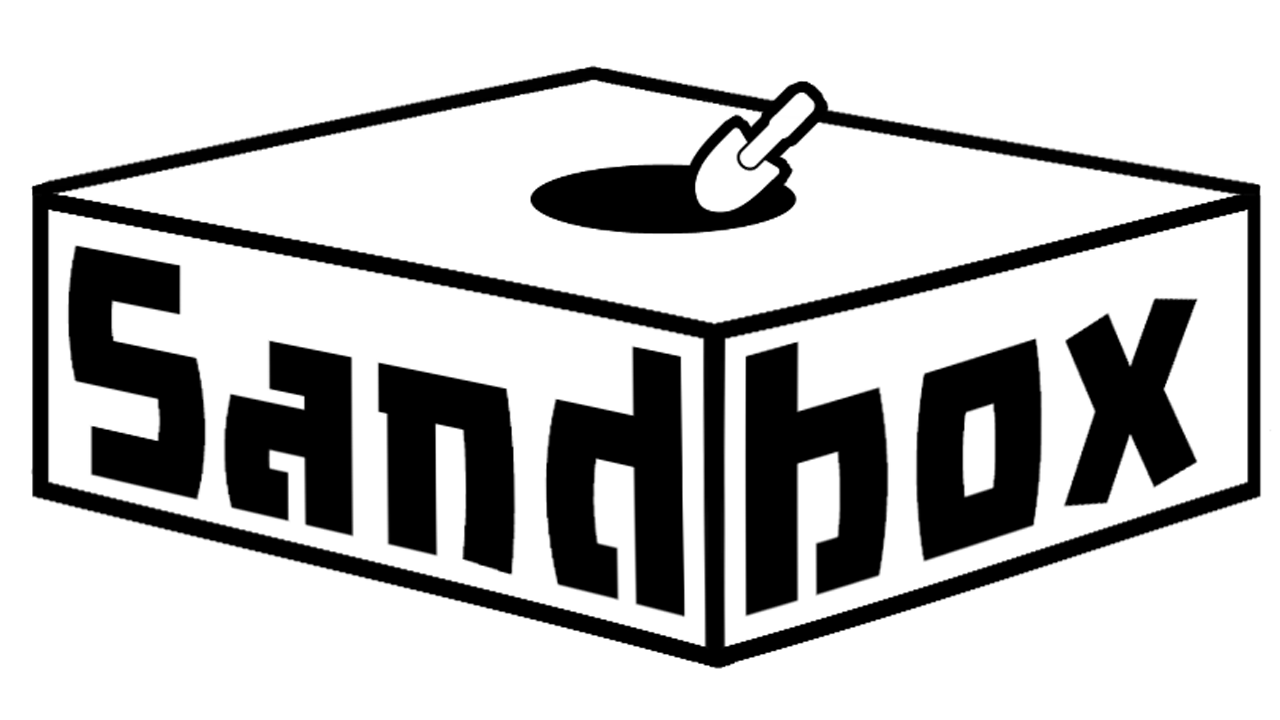


コメント